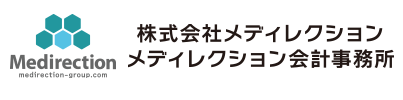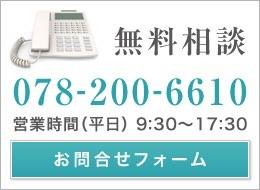事業承継支援
病院・クリニックをはじめとする事業の承継について、悩まれている方も多くいらっしゃいます。事業承継は、年々増加傾向にあるお悩みの一つです。クライアント様のご状況やご事情によって、適した方法も異なります。そのため、お悩みがある場合は専門家に依頼することが重要です。当社では事業承継に関するサポートも行っており、ご要望に沿った最適なプランをご提案いたします。
事業承継は近年増加しているお悩みです
病院、クリニック、医療法人などを取り巻く経営環境は複雑化する一方です。また、経営者の高齢化に伴い、次世代への引継ぎを考え出している医療機関も多くみられます。このような環境下で、病院、医療法人、クリニックが今後も地域で医療行為を継続的に行うために、事業承継を検討するケースが近年は増加しております。しかし、事業承継を検討する場合、開設主体が個人であるか医療法人であるか、子などの親族へ承継なのか第三者への承継なのかで留意すべき点は異なります。
開設主体が個人の場合の承継のポイント
開設主体が個人である場合、事業承継が親族への承継であっても第三者への承継であっても、開設者及び施設管理者が交代することに変わりなく、進めていく手続きとしては大きく異ならず、承継元の現院長の廃業の手続きと承継先の新院長の開業の手続きを要します。特に、親族への承継であると、新たな開設であるといった意識が働きにくく、保険医療機関の指定申請書や診療所開設届など所定の期限までに提出することを忘れやすくなるため注意が必要です。また、親族への承継の種類の一つとしては相続もありますが、この場合においては10年単位での対応が必要になってきます。将来的にご子息様への事業承継を検討しているのであれば、いざというときに備えて早めに対応を検討しておくことが必要です。
開設主体が医療法人の場合の承継のポイント
開設主体が医療法人である場合は、承継元の現院長(理事長)の出資持分の承継と理事長職及び社員の立場の承継をすることで事業を承継していくことができます。持分ありの医療法人において、出資持分の財産価値が大きくなっているケースがよく見られます。出資持分を承継するには贈与や譲渡が考えられますが、いずれにせよ財産価値として大きくなった出資持分の承継には、何も対策を講じなければ発生する税金負担は非常に大きなものとなってしまいます。
第三者への事業承継のポイント
また、後継者の不在によって第三者に事業承継を行う病院、クリニック、医療法人も増えております。開設主体が個人である場合は病院やクリニックの財産(土地、建物、医療用機械、医薬品在庫、診療材料在庫、窓口未収金など)について賃貸や売却の方法によって、承継していくことになります。新規開業に比べて従来からの患者様がいるケースもあるため、付加価値分(営業権)を設定することがありますが、双方が納得いく金額とするためには十分な協議と客観的な判断が必要になります。医療法人を第三者に承継する場合は、現院長(理事長)の出資持分の承継と理事長職の承継を行っていくこととなり、親族への承継と進め方と大きく変わりはありません。しかし、出資持分の評価額はどの程度なのか、その医療法人自体にどれくらいの価値があるのかは第三者間の取引となるため慎重に把握する必要があります。この段階では、承継元の医療法人について調査を行うことも多く、いわゆるデューデリジェンスが行われることもあります。
地域の安定的な医療のために私たちにご相談ください
クリニックや病院はその地域の医療を担っており、地域住民からは継続的・安定的に診療を行うことが期待されています。事業承継にあたっては、手続きや税金など、上述のように留意しなければいけない点は確かに多くありますが、一番しっかりと承継しなければいけないことは地域の患者様からの信頼であるといえます。そのため、承継にあたっては患者様に対するケアだけでなく、クリニックや病院で普段患者様に接している職員についてもケアを図りつつ承継を進めていく必要があります。私たちは、地域の安定的な医療のために、スムーズな事業承継の方法についてご支援していきたいと考えております。